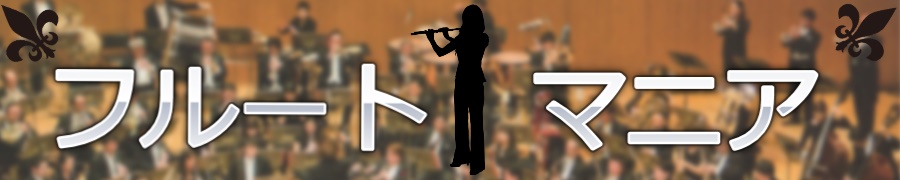なんとなくそれをイメージしながら、まずは持ち方から始めてみましょう。
その後、持つときの姿勢、それから音の出し方を覚えていきましょう。
ではまずは、持ち方です。
フルートの持ち方
初めに、楽器の正しい持ち方を身につけることが大切です。
フルートは、吹き口のある頭部管が左側に、一番端の足部管が顔から一番遠い右側にくるように持ちます。
ただ持てばよいわけではなく、バランスよく持つ必要があります。
バランスの悪い持ち方をすると、演奏する際に指がまわらなくなってしまう、なんていうことも出てきてしまうからです。
バランスよく持つために、3つのポイントで楽器を支えます。
左手人差し指の付け根、右手親指、そしてあご、の3箇所です。
これを頭に入れながら、楽器を持ってみましょう。最初は慣れないかもしれません。
特に、左手が利き手でない人は、慣れるまで大変かもしれませんが、楽器から離れないようにがんばって慣れましょう!
支えることに集中して力が入ってしまうと、すぐに疲れてしまいます。なるべくふんわりと持つようにし、肩の力を入れすぎないよう力を抜いて持ちましょう。
吹く時の姿勢
フルートを吹いている人は、姿勢がよく、凛として見えますよね。演奏には正しい姿勢も大切です。
立って吹く場合は、まず足を肩幅ぐらいに広げて立ちます。
右足を後ろにひいて、正面に対して少し斜めになるようにします。
このようにして立つと、正面に対して、顔とフルートが平行になるようにすることができます。
肩幅に足を広げるのは、体がぐらぐらしたりしないよう、安定させるためです。足先を逆ハの字にして、さらに安定させるようにしてもよいでしょう。
背筋はあまりピンとしすぎると、吹く時に疲れてしまいますので、楽にしましょう。
この状態で、フルートを持ってみます。
正しい姿勢をとったまま、自然に楽器を持てるように、あまり高すぎない位置で持ちます。
ひじは体からほどよく離します。
座って吹く場合も、基本的には同じように姿勢をとります。
演奏に慣れてくると、徐々に姿勢が崩れてくることがあります。
とくに、楽譜を見て曲を吹くようになると、楽譜を見るために左足の方に重心が寄ってしまい、前のめりになってしまいがちです。なるべく、重心は体の真ん中におくようにしましょう。
姿勢は、必ずフルートの音に影響してきますから、いまのうちにしっかりと体に叩き込みましょう!
音の出し方
さて肝心なのは、音の出し方です。
フルートって、他の木管楽器と違って、リードがありませんよね。
どうやって音を出すのか不思議に思いませんか?
フルートはエアリード楽器と呼ばれていて、リードではなく吹き込む息で空気をふるわせることで音を発生させます。
ですから、空気がリードの代わりということなんですね。
フルートに限らず、吹奏楽器は沢山の息を使うことになります。
そのため演奏するときは、たっぷりと呼吸ができる腹式呼吸を使います。
腹式呼吸と言われると、なんとなく難しそうに聴こえますが、実は普段から誰もがやっています。
仰向けになって寝てみるとよく分かると思います。
呼吸をすると、お腹が動いていますよね!
起きて活動している間は胸で呼吸していても、寝ている間は腹式呼吸をしているんです。
腹式呼吸で演奏できるように、このお腹が動く感じを覚えておきましょう。
音を出すために、まずリッププレートに下唇をあてて、楽器の歌口に向かって息を吹き込んでみましょう。
ろうそうの火を消すときのように、フーっと吹くと・・・音が出ませんか?
子どもの頃に、ビンに息を吹き込んでボーっという音を出したことがある人なら、そんなイメージで吹いてもよいでしょう。
うまく音が出ない場合は、頭部管を外側や内側に向けてみるなどして、角度を変えてみて下さい。
また、唇の穴と歌口の中心の位置が合っているかどうか、鏡でチェックしてみましょう。
息がうまく、歌口のエッジと呼ばれる部分にあたっていると、音が出ます。
一度音を出すコツをつかんでしまえば、誰でもフルートを吹くことができます!
頭部管で音が出るようになったら、さっそく本体に接続して、フルートの音をだしてみましょう!
ここまでできたら、スタートラインに立ったようなもの!
上達にむけて、どんどん練習をすすめていきましょう。
もし、練習の中でうまく音が出なくなってしまった、なんてことがあったら、一度、姿勢や吹き方を見直してみましょう。
一番の基本をしっかりと整えれば、解決できる可能性があります!